ニューヒロイン、「アウシュヴィッツの図書係」。【★★★★★】

アウシュヴィッツの図書係/アントニオ・G・イトウルベ 訳:小原京子
図書館に返してしまう1時間前なので急いで感想を書きます。
あらすじ
アウシュヴィッツでは本の持ち込みは禁止されている。読むなんてもってのほか。
国際的な世間体のために存在する三十一号棟。そこでは教室が開かれ、子どもたちは教科書もなく勉強をする。校長のフレディ・ヒルシュから図書係を任命された少女、ディタ(本名:エディタ)。存在してはいけない秘密の本を貸し出し、SSに見つからないように管理する。
頼れるユダヤ人リーダーのヒルシュの秘密を知ったディタの動揺、SSとユダヤ人の恋、収容されているユダヤ人同士での軋轢。寒い冬の、冷たい地獄の世界がそこにある。
親友マルギットとの友情、そして戦争が終わるまでディタを守り抜いた母。
地獄の中を日々どう生きるかは、自分自身であることを教えてくれる。
また、勇気を与えるフレディ・ヒルシュの存在、アウシュヴィッツの悲惨な状況を世界に伝えたルディ・ローゼンバーグの功績も同時に伝えてくれる。実話を元にしたフィクション。
忘れがたきシーン
心揺さぶられたシーンを取り出していきます。
戦争なの。
戦争なのよ、エディタ。戦争なの。
エディタの故郷プラハが侵攻されても、戦争をわからず無邪気に遊ぼうとするディタに母が諭すシーン。興味本位で人前に出たり目立つ行為をすると連行される。子供であっても。日常がどんどん奪われていく。もう、戦争はすぐそこまで来ている。
友だちの存在
頭がどうかなりそうだったが、目を閉じると、一つの光景が浮かんできた。雪の上に倒れ込んでいるマルギットとディタ、それを見ているレネー。三人とも大笑いしている。
こうして笑っている限り、私たちは大丈夫。
人体実験をしていると噂の医師、メンゲレに目をつけられたディタ。メンゲレに対する恐怖心でピリピリ過ごしていた。他にも悩みの種はあるが友人3人で集まってお話して笑い合う。それだけで、心は別のところに飛んだように軽くなる。
どんなつらい状況でも、笑い合える仲間がいれば大丈夫。そんなディタたちに勇気をもらえる。今、戦争が終わった現代の私たちの悩みがどれだけちっぽけか。笑い飛ばせるくらい軽くなる。
モルゲンシュテルン
頭のおかしい滑稽な年寄のまなざしではなく、穏やかな人物の深く優しい表情だった。そのとき、ディタの疑いは消えた。
「モルデンシュテルン先生!」
(中略)フレディ・ヒルシュは言った。ここには見かけどおりのものなど何もないと。別れのキスをしかたったが、それはかなわない。先生はおどけて遠ざかり、去っていく人たちの波に飲み込まれた。
雪を網でつかまえて遊ぶくらい頭がヘンテコなおじいさん、と思われていた人だが実際は哲学的で心優しい人物だった。父が亡くなり憎しみに囚われたディタを優しくなだめるなど、人間としての懐の大きさはかなり広い。そんなモルゲンシュテルン先生が移送(どこに連れて行かれるかわからない、つまりこれから死ぬ)される列を歩いているシーン。泣ける。
ヒルシュの名言「ここには見かけどおりのものなど何もない」もあるので同じく載せておく。
私はリダよ!
女性の一団が通り過ぎる。(中略)一人が、命令のまま粛々と進む行進の列を離れ、ディタの方にやってきた。最初は誰だかわからなったが、それはディタのベッド仲間の大女だった。もつれた髪が顔の大きな傷跡を隠している。二人は一瞬じっと見つめ合った。
「私はリダよ!」野太い声で言う。
カポーが飛んできて、すぐに列に戻れとわめき始めた。そして脅すようにこん棒を振り回す。急いで列に戻りながら、彼女はまたちらっと振り返って手を振った。
「元気でね、リダ!素敵な名前ね!」とディタは叫んだ。
リダは誇らしげに微笑んでいた。
正直に言ってこのシーンが一番グッと来た。
ディタがアウシュヴィッツに連行された日、寝床を自分で確保しないといけなかった。ベッドなんて一人ひとつあるわけない。入れてくれそうなところを探すが、誰だって自分の寝床に人なんて入れたくないのである。同じ囚われのユダヤ人であっても譲り合う・分け合うなんて気持ちはない。
そんな中ディタが見つけたのは見るからに強そうな大女のベッド。思い切って入り、なんとか寝床として使うのを許された。大女には挨拶をしても返事はない。会話らしい会話もしたことがない。名前も知らないままだった。
それでこの大女がディタに最後の別れを言いに来るシーンである。
心やさしきモルゲンシュテルン先生の別れの後にまさかのベッドの大女という2コンボが強すぎてさすがに目頭が熱くなった。なんで良い人ばっかりこんな目に遭うんだよ…。
読み終えた感想
戦争よ、早く終われってどれだけ思ったか!
実話に基づいているから日付も記されてるんだけど1944年って見るとあああああああああああああああってなる。あと1年もあるのかと嘆いてしまう。
ディタはたしか14~15歳で「思春期のときの1年は永遠なのよ」と名セリフを作中で吐くくらい。わかる。そんな大事な1年戦争で過ごすとか。
あと、ルディ・ローゼンバーグという収容所の登録係が脱走し、ユダヤ人議会でアウシュヴィッツの陰惨な現状を報告するシーン。まさかの議会だれも信じない。ファッ!!!???
それでもヒルシュの影響を受けていたルディは屈せず、イギリスに渡り報告していく。なんてたくましい。というかそんなことがあったの知らなかった。。。ルディ・ローゼンバーグという勇気ある人の功績を知ることができてよかった。
しかし……ディタやヒルシュはどれだけ強いのか。実際はそれぞれ弱いところがあるんだけど、かつて人類が味わったことのないような過酷な状況下でも希望を捨てなかった。それが、現代という日常を生きる私にどれだけ力強い光を与えてくれたか。
実はこの感想を残そうと思ったのは、「アウシュヴィッツの図書係」を読んでから自分の行動や意識が変わったのを実感しているから。
アウシュヴィッツの大人が先生になり、自分が話せる物語を聞かせることで子供たちは別の世界に行ける。別名「生きた本」。本物の本がなくても、自分の中に本はある。知は力なり、とはよく言ったものだと思う。自分にできることをする。ほんの少しであっても希望や楽しみが他者に生まれるのだとようやく気づいた。
私も、どんな状況でも他者に与えることは忘れたくない。でも、例えば日本の戦中に戻ったとして自分は誰かを見守ったり優しくしたりすることができるだろうか?自信がない。親戚の子供兄妹が疎開で田舎に来たら冷たくあたって、彼らに出ていかれて兄は妹を餓死させるに違いない。
そういえばフジコ・ヘミングはどんなに自分が貧しいときも犬や猫の世話はしていた。与える気持ちは大事にしていると本で見かけたことを思い出した。
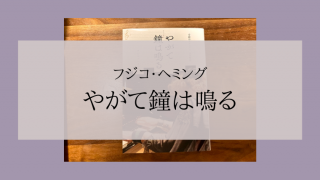
ものがなくても、自分が見て知ったことはたくさんある。それなら、今からでも誰かにあげられる。
与える喜びっていう大事なものに、32歳冬気づきました。
最後に
まとめません。
鉄は熱いうちに打て、というので勢いのまま書きました。
将来の私に忘れてほしくないから書き残したのが当初の目的なので、かなり読みにくい部分もあると思いますがご容赦ください。
ニューヒロイン、というのはあとがきにあった言葉。本当にしっくりきたので使わせていただきました。
エディタ、ヒルシュに大きな尊敬の念を。




